人生の中で、自分の大切な財産を次の世代にスムーズに引き継ぐための方法の一つが「生前贈与」です。
生前贈与とは、自分が生きている間に配偶者や子ども、孫に財産を贈ることを指し、税制上の特典や節税効果も期待できる仕組みです。
ただし、贈与の方法にはルールや注意点があり、活用次第で家族のトラブルを避け、安心して資産を渡すことができます。
この記事では、生前贈与の基本的な制度やメリット、非課税で利用できる特例などをわかりやすく解説し、安心して活用するためのポイントを紹介します。
生前贈与とは
生前贈与とは、自分がまだ生きている間に配偶者や子ども、孫などに財産を渡す方法のことをいいます。
財産を受け取る側は「贈与税」の対象になりますが、日本では贈与税を軽減・回避できる制度も設けられています。
生前贈与の代表的な制度には、「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の2つがあります。
相続時精算課税制度
原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子どもや孫へ贈与する際に選択できる制度です。
贈与時には一定額まで贈与税がかかりませんが、贈与した金額は将来の相続時に相続財産に加算され、その合計額に対して相続税が計算されます。
年間110万円の基礎控除に加え、最大2,500万円までの特別控除があり、超過分には一律20%の贈与税がかかります。
なお、税務署への申告が必要です。
暦年贈与
1月1日から12月31日までの1年間に、一人につき110万円までの贈与は非課税で、申告も不要です。
贈与額がこの基礎控除内に収まれば、贈与税はかかりません。
生前贈与のメリット
生前贈与の最大のメリットは、相続税や贈与税の節税効果が期待できることです。
生前に計画的に財産を贈与することで、相続時の財産総額を減らし、結果として相続税の負担を軽減できます。
また、贈与する相手やタイミングを自分で決められるため、財産の行き先をコントロールしやすいのも特徴です。
例えば、相続人間のトラブル防止のために特定の子どもや孫に贈与を集中させたり、相続分配を調整したりすることができます。
さらに、これから価値が上がりそうな財産(株式や不動産など)を、値段がまだ低いうちに贈与すると、相続時に高騰していたとしても贈与時の価額が適用されるため、節税につながる可能性があります。
こうしたメリットを活かすためには、贈与の方法やタイミングをしっかり検討し、計画的に行うことが重要です。
非課税で生前贈与できる方法
生前贈与にはいくつかの非課税制度があり、それぞれ向いているケースや条件が異なります。
主な方法を解説します。
暦年贈与
1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
この基礎控除を利用して少しずつ贈与を続ける方法です。
【向いているケース】
- 贈与者がまだ高齢でない場合
- 毎年コツコツ贈与したい場合
- 将来的に相続しない可能性がある孫などへの贈与にも有効
相続時精算課税制度
累積贈与額が最大2,500万円まで非課税となり、その分は相続財産に加算されて相続税が計算されます。
超過分は20%の贈与税がかかります。
【向いているケース】
- 高齢の資産保有者が一度にまとまった資産を贈与したいとき
- 不動産や株式など将来値上がりが予想される資産を贈与したい場合
住宅取得等資金の贈与の特例
2024年1月1日から2026年12月31日まで、直系尊属から住宅の新築や増築資金を贈与された場合、省エネ住宅は最大1,000万円まで、その他の住宅は最大500万円まで贈与税が非課税となります。
【向いているケース】
- 子どもや孫が住宅取得や増改築を計画している場合
教育資金の一括贈与の特例
30歳未満の子や孫に教育資金として一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税。
ただし金融機関との契約と管理が必要です。
参照:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
【向いているケース】
- 一括でまとまった教育資金を贈与したい場合
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
18歳以上50歳未満の子や孫に結婚や子育て費用を贈与する場合、最大1,000万円(結婚費用は300万円まで)が非課税。
参照:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
【向いているケース】
- 結婚や子育て費用を支援したい場合
配偶者控除
結婚20年以上の配偶者に自宅や購入資金を贈与した場合、基礎控除に加え2,000万円まで非課税。適用は一生に一度で、贈与後の居住条件あり。
【向いているケース】
- 配偶者の住まいを安定させたい場合
生前贈与する際の注意点
生前贈与を行う際は、いくつかの注意点があります。
遺留分を侵害しない範囲内で贈与する
遺留分とは、法律で保障された相続人の最低限の取り分です。
これを大きく侵害すると、相続後にトラブルが発生する可能性があります。
死亡直前の贈与は相続税の対象になる場合がある
亡くなる直前の贈与は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になることがあるため注意が必要です。
「定期贈与」には注意
毎年決まった額を同じ人に贈与する「定期贈与」は、税務署から認められないケースもあるため、計画的に行いましょう。
「名義預金」
実態が伴わない名義預金は、税務上認められません。
贈与のし過ぎ
贈与のし過ぎも家計を圧迫したり、逆にトラブルを招く恐れがありますので、無理のない範囲で行うことが大切です。
専門家に相談しながら進めよう
生前贈与には多くの制度や特例があり、上手に活用すれば税負担の軽減や家族間の円満な財産承継に役立ちます。
ただし、複雑なルールやケースごとの適用条件があるため、自己判断だけで進めるのはリスクも伴います。
特に高額な贈与や不動産の贈与、相続対策としての生前贈与は、税理士や弁護士といった専門家のアドバイスを受けることが重要です。
適切な手続きや書類の作成も含めて、安心して進められるようにしましょう。
生前贈与は家族の未来を守る大切な手段。
ぜひ信頼できる専門家と相談しながら、最適な方法を選んでください。


.png)
.png)
.png)


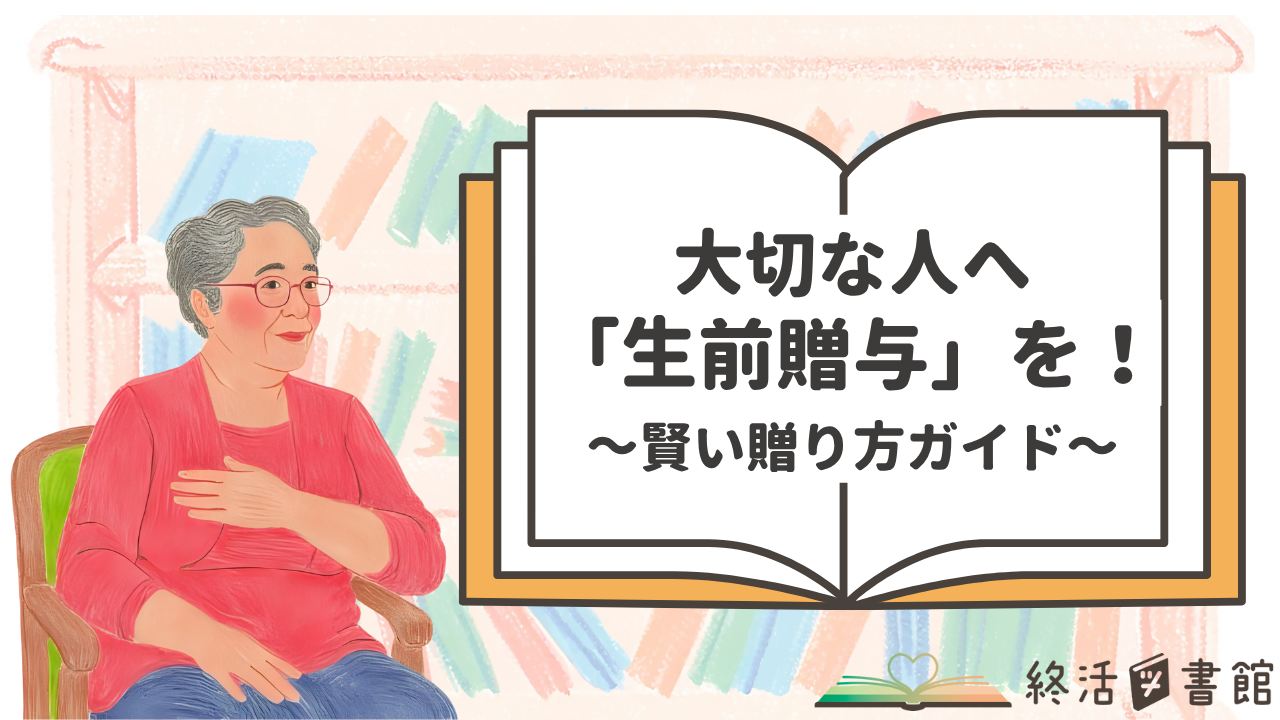

.png)
.png)


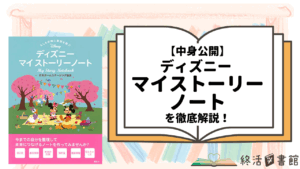
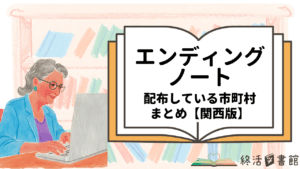
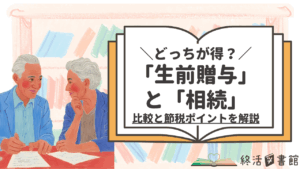







コメント