高齢化が進む現代、日本では高齢者同士で介護を行う「老老介護」が増えています。
本人たちだけでは抱えきれない負担やリスクもあり、子供世代ができるサポートを知ることが大切です。
今回は、老老介護の現状や課題、そして子供世代ができる具体的な支援方法を整理しました。
老老介護とは?
老老介護とは、高齢者が高齢の配偶者や親を介護する状態を指し、一般的には65歳以上の高齢者が要介護者を支えるケースを言います。
高齢者同士で介護を行う場合、体力や判断力の低下、持病の影響などで、介護の負担が大きくなりやすい特徴があります。
老老介護は身体的負担だけでなく、精神的・社会的負担も伴います。
長時間の介護や孤立感によって、うつ症状や認知機能の低下が生じるリスクがあります。
さらに、医療や介護の知識が十分でない場合、介護ミスや体調変化の見逃しなどの危険も高まります。
そのため、老老介護は単なる「日常生活の支援」にとどまらず、家族や地域のサポートが不可欠な状況と言えます。
早めに制度やサービスを知り、支援体制を整えることが、本人と介護者双方の安心につながります。
増える老老介護
なぜ老老介護が増えているのでしょうか。その背景を見ていきましょう。
高齢化
日本の高齢者人口は年々増加しており、介護を必要とする高齢者も増えています。
核家族世帯の増加
子供世帯が遠方に住む場合、介護を担うのが高齢の配偶者になるケースが増えています。
平均寿命・健康寿命の差
高齢者の平均寿命は延びているものの、健康寿命との差によって介護が必要な期間も長くなっています。
老老介護の割合
実際にどれくらいの高齢者が老老介護を行っているのでしょうか。
厚生労働省の「2022年 国民生活基礎調査」によると、在宅介護をしている家庭のうち、65歳以上の高齢者が要介護者を介護する「老老介護」の割合は63.5%に達しており、過去最高の数値となっています。
さらに、介護する人とされる人がともに75歳以上の「超老老介護」の割合も35.7%と増加しており、今後もこの傾向は続くと予想されます。
このデータからも、高齢者同士で介護を行う家庭が増えている現状が見えてきます。
体力や判断力の低下によるリスクや負担の大きさを理解し、早めの支援や制度活用が重要です。
老老介護によって起きている問題
老々介護にはさまざまな問題があるといわれていますが、具体的にどのような問題があるのでしょうか。
身体的、心理的な負担の増加
介護による重労働だけでなく、ストレスや孤独感などの精神的な負担も大きくなります。
経済的な問題
年金生活の中で介護費用が増加し、生活に影響が出ることがあります。
ネグレクトの原因になる
高齢者同士だと、体力や判断力の低下で食事や入浴などの日常生活のケアが不十分になる場合があります。
特に認知症や持病がある場合、必要なケアを見逃すリスクが高まります。
介護疲れで共倒れになる可能性がある
長時間の介護や精神的ストレスが続くと、介護者自身が体調を崩したりうつ状態になることがあります。
介護者が倒れると被介護者も支援が受けられなくなり、共倒れの危険があります。
認知機能の低下により体調の変化に気付けない
高齢者が介護を担う場合、血圧の変動や体温の上昇など小さな変化に気づきにくくなります。
これが病気の早期発見を遅らせる要因になります。
周囲に相談できず社会的な関わりが少なくなる
介護に専念するあまり、親族や地域との交流が減り、孤立感や孤独感が強まることがあります。
精神的負担の増加や支援機会の減少にもつながります。
知っておきたい介護サービスの活用と制度
皆さんは介護サービスや制度があることをご存じでしょうか。
サービスや制度を上手に活用することで、介護の負担を大幅に軽減できます。
厚生労働省㏋ 介護保険制度の概要
介護保険制度
65歳以上の方は介護保険を利用して、訪問介護やデイサービス、ショートステイ、福祉用具貸与などさまざまなサービスを受けられます。
介護者が無理なく休息できるよう、ショートステイを活用するのも有効です。
地域包括支援センター
高齢者や家族の相談窓口で、生活支援、医療、介護に関する相談や情報提供をしてくれます。
ケアマネジャーとの連携を通じて、最適な介護プランやサービスを提案してもらえます。
在宅支援サービス
訪問看護や訪問リハビリを組み合わせることで、医療的ケアが必要な高齢者も自宅で安全に暮らせる環境を整えられます。
子供世代ができるサポート
核家族化が進行し、高齢の親と離れて暮らす子供世代も少なくありません。
ここでは、子供世代が老老介護に直面する親にできるサポートをご紹介します。
コミュニケーションの強化
介護者である親の気持ちや話を聞き、共感と理解を示すことが精神的支えになります。
悩みを聞き、一緒に解決策を考えることも大きなサポートになります。
日常生活のサポート
定期的な買い物、掃除、料理などの手助けや、通院の付き添い、送迎も介護者の負担軽減につながります。
補助金や助成金の申請
介護リフォームで利用できる補助金や、介護休業給付など、経済的支援も積極的に活用しましょう。
介護認定の区分変更申請を依頼する
高齢者の状態は変化します。
必要に応じて介護度の見直しを行うことで、受けられるサービスの幅が広がり、負担を軽減できます。
訪問サービス・介護サービスを利用する
デイサービス、訪問介護、訪問入浴などを組み合わせ、親の生活を支援しつつ、介護者が休息をとれる環境を作ります。
家族・地域と協力できる体制を整えておく
兄弟姉妹や親族と役割分担を話し合い、近隣住民やボランティアも活用することで、孤立を防ぎます。
地域包括支援センターやケアマネジャーと現状を共有する
日常の状況や課題を共有し、必要な支援やサービスの調整を行ってもらうことで、より安全に介護を行えます。
老人ホームへの入居を検討する
在宅での介護が困難な場合、施設利用も視野に入れることで、家族全体の負担を軽減できます。
施設によって医療対応やリハビリ環境が整っているので、安心して預けることができます。
老老介護は家族全員で取り組む問題
高齢者同士の介護は、身体的・精神的負担が大きく、放置するとトラブルや健康被害につながる可能性があります。
子供世代が積極的に関わり、介護サービスや地域資源を活用することで、老老介護を抱える家族の負担を軽減できます。
家族全員で情報を共有し、相談できる体制を整えることが大切です。


.png)
.png)
.png)


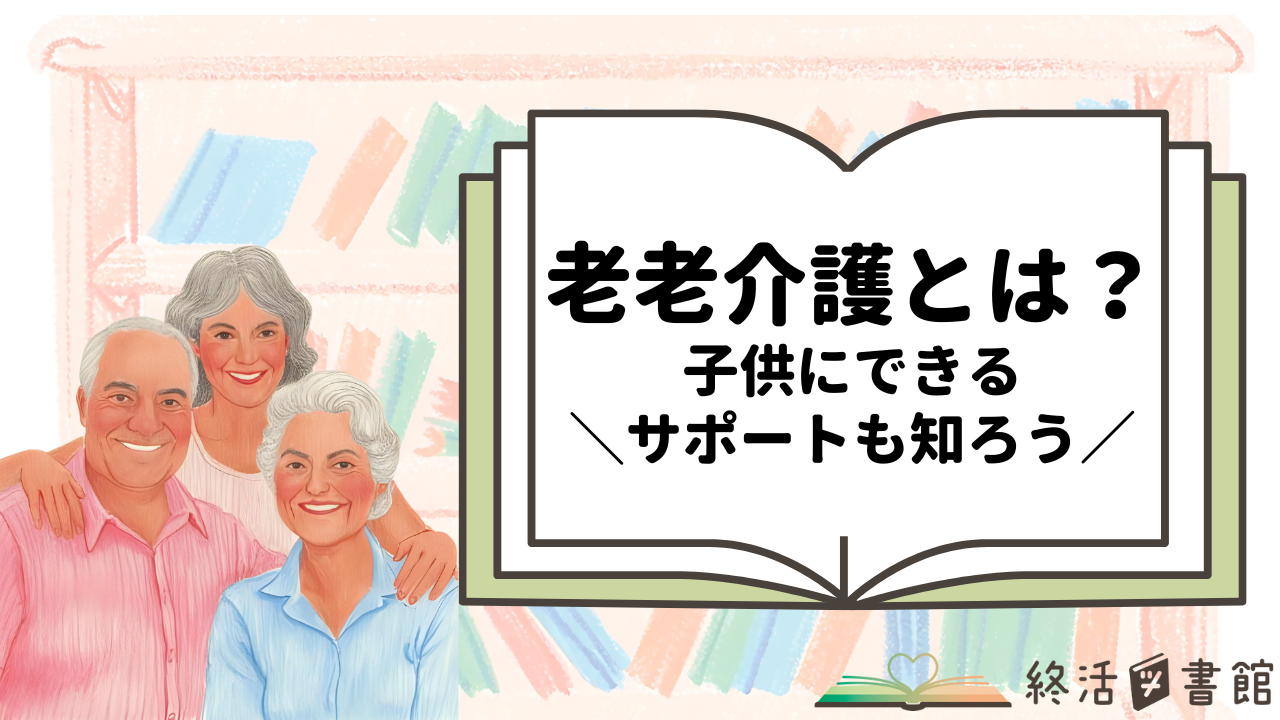

.png)
.png)



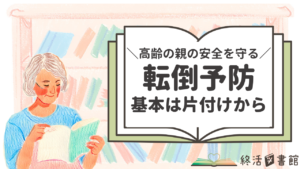


-300x169.png)
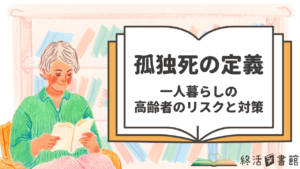
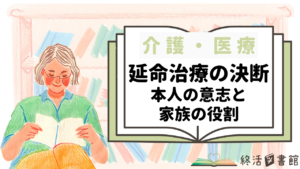


コメント