高齢の両親や親族が家のことが出来なくなる前に、「整理したい」「片づけたい」と思っている方もいるでしょう。
そして、実際に片づけようとしても思うように進まず、困っている方もいるかもしれません。
しかし、高齢者には部屋や身の回りを片づけられない理由があります。
性格だけでなく年齢に伴う体の変化などの影響もあるのです。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷周囲のサポートやアプローチで、解決出来るかもしれません。
今回の記事では高齢者が片づけられない理由、片づけないと起こるリスクと高齢者と一緒に片づけを行う際のポイントを紹介します。
高齢者が片づけられなくて困っている方や生前整理をしようと思っている方、ぜひ参考にしてみてください。
高齢者が“片づけられない”理由
高齢者が“片づけられない”主な理由は以下4つです。
- 幼少期の環境(戦争や貧困)
- 体力や気力の衰え
- 子や孫に迷惑をかけたくないと思っている
- 認知症の影響
次の項目で順番に説明していきます。
幼少期の環境
日本が経済的に豊かになったのは、高度経済成長を迎えた1970年代です。
80代前後の高齢者の幼少期は、戦争真っ只中で経済的な余裕は無かった時代でした。
戦争や貧困を経験しているため、「捨てるのがもったいない」と考える傾向が強いと言われています。
過去の経験から、現代人と比べて物に対する執着心の強さが特徴です。
弊社の現場でも、他人からの頂き物(食器、タオル、タオルケット)や、誰かが来た時のための布団が大量に残されるケースも少なくありません。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷物を大切にするあまり、気付いたら増えてしまい片づけられない可能性があります。
体力や気力の衰え
上記のように物がどんどん増えてしまい、「片づけよう」と思っても以下の理由で片づけられない可能性が高いです。
- 体力が衰え1人では出来ない
- 何から手を付ければ良いか分からず、気が滅入る
- 急いでやる必要性を感じない(あと回しになる)
体力的な問題だと、粗大ゴミの搬出や2階の部屋に上がれないなどです。
また、無理して片づけを行うと、最悪の場合骨折など怪我につながる可能性もあります。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷実際の現場でも、とりあえず物を押し込んで、何が入っているか分からなくなり、手をつけられず放置されているケースもよくあります。
また、気力の衰えから、急いで行う必要性も感じていない可能性も高いです。
周囲に迷惑をかけたくないと思っている
高齢者によくある傾向で、家族や周囲に「迷惑をかけたくない」と思っているかもしれません。
「迷惑をかけたくない」と思ってしまう理由は、身の回りの掃除や片づけが出来ない自分が恥ずかしく、自尊心に関わるデリケートな事柄だからです。
そのため、家族に手伝いを求められない高齢者も多いと言われています。
結果的に、身の回りを片づけられず、状況が悪化してしまうケースも多いです。
認知症の影響
「片づけられない」状況は、認知症の初期症状の場合も考えられます。
認知症により、片づけられない理由は以下の3つです。
- 捨てる物と捨てない物の区別ができない
- ゴミ箱を置いた場所を忘れてしまい、ゴミを周囲に置いてしまう
- ゴミ出しの日時や場所が分からない
上記の症状が見られた場合、認知症の影響で片づけられないのかもしれません。
また、認知症は現段階では完治が難しい病気と言われています。
- 高齢者になって社会との繋がりが希薄になった
- 定年退職をして人との交流がなくなった
- 妻や夫に先立たれて孤独になった
周囲との繋がりがなくなると、認知症になるリスクが高いです。
実際に認知症の患者数は増加傾向にあり、日本人の65歳以上の認知症者の数は、2012年は462万人(高齢者の7人に1人)でした。
しかし、2025年には650〜700万人(高齢者の5人に1人)に増加すると予測されています。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷認知症は家族のサポートも重要になるため、家への帰省回数を増やすなど、認知症のリスクを減らす関わりも大切になります。
【参照】国立精神・神経医療研究センタ
家のなかを片づけないと起こるリスク
高齢者が家のなかを片づけないと起こるリスクは 主に3つあります。
- 火災
- 転倒や転落
- 病気や感染症
以上の3つを詳しく説明します。
火災
たまった埃がコンセントにかぶり、引火して火災になる可能性が高いです。
また、火事になった際にたくさんのゴミや物があると、燃え広がったり、逃げ遅れる可能性も高くなります。
転倒や転落
平坦な場所でも、高齢者は筋力が弱っているため、バランスを崩し転倒する可能性があります。
家が散らかっていると、足元に物が多いため転倒や転倒のリスクは高いです。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷話は逸れますが、賃貸の場合は床が極端に汚れていたり、畳にカビが生えていると修繕費が多くかかる可能性もあります。
病気や感染症
害虫や悪臭で不衛生な環境は、病気や感染症を引き起こしやすくなります。
害虫が発生しても、物が散らかった環境では徹底的な退治も難しいです。
また、賞味期限切れのものや、カビの生えたものを食べてしまうリスクもあるでしょう。
もし病気になっても、認知症の影響で病気に気付いてなかったり、気力の低下から面倒に思って病院を受診しない可能性があります。
高齢者と一緒に片づけを行うポイント
高齢者の家を一緒に片付けようと思っている方もいるでしょう。
高齢者と一緒に片づけを行う際のポイントは6つあります。
- 「捨てる」や「処分する」などの言葉は使用しない
- 一気に片づけようとしない
- 「必要なもの」と「不要なもの」から仕分ける
- 処分する基準をお互いに決めておく
- 保留スペースを設ける
- リサイクルショップなどの活用
具体的に説明していきます。
①「捨てる」や「処分する」などの言葉は使用しない
「捨てる」や「処分する」など、ネガティブに受け取られそうな言葉は使わないようにしましょう。
理由は、「これはいらないでしょ」や「邪魔だから処分しよう」と言っていきなり片づけると、物を粗末にできない高齢者の方は嫌がるからです。
あくまで決めるのは本人なので、周りの人は本人の意思を尊重しサポートをする形をとりましょう。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷「壊れているけどまだ使う?」「同じものが2つあるけど、どうする?」などのように、本人に決断してもらえるような問いかけで進めると気分を害することが少ないでしょう。
②一気に片づけようとしない
すでに散らかった部屋を片づける時は、定期的に少しずつ進めるのがポイントです。
一度に片づけようとすると、互いに時間と体力を使う上に気持ちの上でも面倒になります。
「散らかっているなら、放っておいても同じ」とあと回しにしてしまい、余計に散らかる可能性も出てくるでしょう。
たとえば「毎週末に2時間片づける」と決めてしまえば、さほどストレスを感じずに取り組めるかもしれません。
1ヶ月に1回決まった日に行う場合は、事前にカレンダーに記載を入れてしまう方法もおすすめです。
③「必要なもの」と「不要なもの」から仕分ける
まだ使う家電や家具、通帳や印鑑など必要なものは事前にメモしておきます。
貴重品のみを入れる貴重品ボックスを用意するのも良いでしょう。
必要なものをリストアップする際、保管場所もあらかじめ決めておくと片づけがスムーズに進みます。
また、「親にとって思い入れのあるもの」や「思い出の品」も確認し、経験や思い出は分けて保管するとスムーズです。
④処分する基準をお互いに決めておく
必要なものを仕分けたが、捨てたくないものが多くなる可能性もあります。
実際、捨てたくないものは長期間使用していない場合が多いです。
「半年使用しなければ処分」や「1年使用しなければ処分」など、処分する基準を決めておけば、整理する習慣にもなります。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷また、決めた内容はメモで残す、専用の保管ボックスに入れて定期的に見直せるようにするなど高齢者がわかるようにしておく工夫も必要です。
⑤保留スペースを設ける
高齢者にとって、いきなり不要品を捨てるのは相当なストレスがかかります。
「捨てる」決断は負担になるので、片づけを途中で諦めてしまう可能性もあるでしょう。
片づけを続けるためには、捨てるか迷うものを保管スペースに置くのがおすすめです。
迷ったものを入れる箱を作れば、「捨てる」決断を減らせるので心の負担が軽くなります。
保留スペースは定期的に見直しを実施すれば、「3ヶ月使っていなかったから捨てる」など、処分の基準を反映させながら整理ができるでしょう。
⑥リサイクルショップ等の活用
不要だが捨てられないものや、まだ使用可能なものはリサイクルショップの活用も検討しましょう。
「捨てる」に抵抗がある高齢者は、使ってくれる人の元に行くと思えば抵抗が少なくなるかもしれません。
家族で片づけが出来ない場合は業者に依頼
本格的に家を片づけるなら、業者に頼むのがおすすめです。
ゴミが山積みになり、足の踏み場もない状態だと自分たちで整理するのは困難でしょう。
高齢の親と家族だけでは、体力的に疲れ果て言い争いに発展したり、怪我のリスクもあります。
専門業者は、短時間で必要なものと不要なものを分別してくれるので、言い争いや怪我のリスクも減るでしょう。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷トラブルを防ぐためにも、片づけをスムーズに行ってくれる専門業者に依頼するのがおすすめです。
高齢者の“片づけ”は周りのサポートで解決できる
高齢になると気力や体力の低下、認知機能の低下など、「片づけられない原因」がたくさんありますが、周りのサポートで解決できるケースが多いです。
しかし、周りの家族や手伝う人が疲れ切ってしまい、本来の目的を見失ってしまう可能性もあります。
周りだけで片づけを行っても良いですが、困っている方はサービスや業者を検討してみても良いでしょう。
高齢者の家の片付けは早めに取り掛かって損はありません。
 思い出コンサルタント 前谷
思い出コンサルタント 前谷さらに、介護保険申請やサービスを調べておくなど、心の余裕を作っておくのも大切です。


.png)
.png)
.png)


-2.png)

.png)
.png)

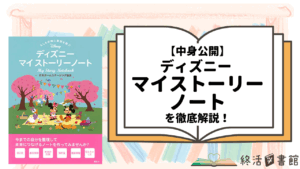
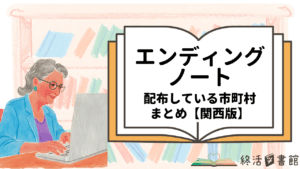
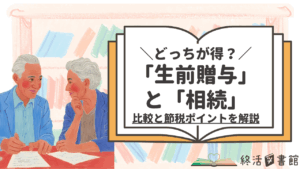
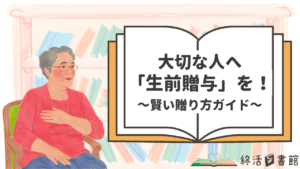






コメント